親子で伸ばす!金融リテラシーシリーズ第4弾です。
過去の記事もぜひチェックしてみてください。
「金利」とは?小学生でもわかる説明
金利とは、簡単にいえば「お金を預けたら、少し増えて返ってくる」仕組みのことです。
銀行にお金を預けると、銀行はそのお金を運用して利益を出し、その一部を預けてくれた人にお礼として返してくれます。これがお金が増える理由であり、その増えた分を「利子」または「利息」と呼びます。
わが家の実践:「お年玉銀行」方式
噛み砕いて説明することで、小学生でも金利は十分理解できます。
わが家ではさらに、実体験を通してより深く理解してもらいたいと思い、次のような仕組みを設けています。
👉 子どもがお年玉をもらったタイミングで、もしその一部を銀行口座に預けたら、
1年後に残っていた金額の 1割 を「利子」として親から支給する、という方法です。
こうすることで、子どもは「お金を預けると増える」という仕組みを、実際に体験を通して実感できるのです。
実際の銀行では金利がとても低いため、子どもに「お金が増える体験」をしてもらうのは難しいのが現状です。そこで家庭内ルールとして“親が利子に近いものを渡す”形をとっています。
**ここでは税金については考慮していませんが、現実には利子にも税金がかかるんだよ、とサラッと伝えるとその後税金の説明をするときに会話が広がるのでおすすめです。
子どもが喜ぶポイントを活かす
子どもは「お金が増える」ことにとても喜びを感じます。この気持ちをうまく利用することで、自然と金融教育につなげることができます。
さらにわが家の場合はお年玉を1年のスタートに預けて、翌年のお年玉の時期に“増えたお金”を返すので、子どもにとって「ちょうど1年で増える」という流れがとてもわかりやすいのです。
なぜ金利を理解しておく必要があるのか
金利を知っているかどうかは、将来の金融リテラシーに直結します。
・借金をするときの「利息」
・預金や投資で得られる「利子」
これらはすべて金利の考え方につながっています。
「お金を借りれば返す額が増える」「預ければお金が少しずつ増える」――この基本を理解しておくことで、将来の金融トラブルを防ぐことができます。
家庭でできる金融教育のヒント
「金利」をテーマにした学びは、子どもが体験して初めて腑に落ちることが多いです。
ぜひお年玉やお小遣いを使って、家庭ならではのルールで実践してみてください。
※ここで大事なポイント:お年玉を全額使うのも、銀行に預けるのも、あくまでも子どもの意思です。
「1年後に増えるから預けなさい!」や「預けた方が得だから」と無理に誘導するのは本末転倒です。
お金の使い方を自分で決める経験こそが、将来の金融リテラシーを育てる大切な一歩になります。
おすすめ教材でさらに理解を深めよう
もし「もう少し体系的に子どもに金融教育をしてみたい」と思ったら、以下のような子ども向け教材もおすすめです。
|
|
本や教材を取り入れることで、「家庭での体験」+「知識の整理」ができ、学びがより深まります。
📚 親子で伸ばす!金融リテラシー シリーズ
- 第1弾:子どもの無駄遣いをどう防ぐ?親子で学ぶお金の基礎
- 第2弾:家庭の資産を子どもに公開!お金の透明性で育つ力
- 第3弾:子どもに伝える給料の違い|時給1000円と5000円で生活はどう変わる?
- 第4弾:【お金教育】小学生に金利をわかりやすく教える!わが家の“お年玉銀行”実践法(この記事)

大丈夫。
いつも頑張っているあなた。
肩の力を抜いて、一緒に前を向いて歩んでいきましょう。



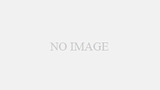
コメント